二十四節気&.七十二候 ☆太陰暦における日付と季節の関係を明らかにし、季節の移り変わりを民にしらせ 農作物の収穫を上げようとの目的で殷代以前の中国で考案された。 日本には奈良時代に伝わり、江戸期に改良された。 一年を二十四に分け、その区分点に季節感あふれる名称がつけられている。 ★24節気をさらにそれぞれ三等分したものを72候というが、 それを日本の気候に合わせて改定したものを記す。 ☆太陽年を太陽の黄経に従って24等分して、季節を示すのに用いる語。 その等分点を立春、雨水などと名づける(広辞苑より) 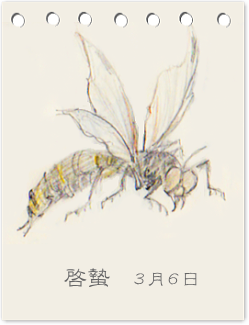 |
| 24節気 | 72候 | ||||
| . | 時 期 (頃) |
黄経 (度) |
意味. | . | 意味 |
| 小 寒 | 1/6 | 285 | 冬至後15日で、この日が「寒の入り」で節分までの約30日間が「寒の内」 | 芹乃栄 | 芹がよく育つ |
| 水泉動 | 凍った泉水が動き始める | ||||
| 雉始雊 | 雄の雉が鳴き始める | ||||
| 大 寒 | 1/20 | 300 | 「寒の内」のちょうど真中の日。 この日から、立春までが年間を通し最も気温が低い時期にあたる。 野は、冬枯れの色になるが、その寒さの中で、 オオイヌノフグリやセイヨウタンポポに出会うこともある。 |
款冬華 | 蕗の薹がでてくる |
| 水沢腹堅 | 沢に氷が厚く張りつめる | ||||
| 鶏始乳 | 鶏が卵を産み始める | ||||
| 立 春 | 2/4 | 315 | 節分の翌日。気温が徐々に上がり、木々が芽吹き始める。 二百十日などはこの日から数える。 オオイヌノフグリなどに出会える。 |
東風解凍 | 東風が厚い氷を解かし始める |
| 黄鶯睍睆 | 鶯が山里で鳴き始める | ||||
| 魚上氷 | 割れた氷の間から魚が飛び出す | ||||
| 雨 水 | 2/18 | 330 | 積もった雪や氷が溶け始め、雪も雨と変わる。梅の蕾がふくらみ ハハコグサ(オギョウ)やホトケノザがさきはじめる。 |
土脉潤起 | 雨が降って土が湿り気を含む |
| 霞始靆 | 霞がたなびき始める | ||||
| 草木萠動 | 草木が芽吹き始める | ||||
| 啓 蟄 | 3/6 | 345 | 地中で冬ごもりしていた虫たちが地上へはいだし活動しだす頃。 ナズナやオニタビラコ、ハコベなど春の七草も咲き始め、シロバナタンポポや西洋タンポポもみられるようになる。 |
蟄虫啓戸 | 冬ごもりの虫が出て来る |
| 桃始笑 | 桃の花がほころび始める | ||||
| 菜虫化蝶 | 青虫が羽化し紋白蝶になる | ||||
| 春 分 | 3/21 | 0 | 太陽の中心が春分点上に来た時で、昼夜の長さがほぼ等しい。 春の彼岸の中日 この頃には、桜の蕾も膨らみ、足元には土筆が顔を出す。 レンゲやカラスノエンドウも野を彩る。 |
雀始巣 | 雀が巣をつくり始める |
| 桜始開 | 桜の花が咲き始める | ||||
| 雷乃発声 | 雷の音がし始める | ||||
| 清 明 | 4/5 | 15 | 『清浄明潔』を略している。 桜の咲き誇る季節、清らかで暖かい春風の吹く頃 ウマノアシガタやキジムシロなどが路辺を飾る。 |
玄鳥至 | 燕が南からやって来る |
| 鴻雁北 | 雁が北へ渡って行く | ||||
| 虹始見 | 雨の後に虹が出始める | ||||
| 穀 雨 | 4/20 | 30 | 春雨が降り、田畑を潤して作物の生長を促す。たねまきに適した頃。 野ではスミレ、二ガナ、春欄、ヨメナ、シロツメクサなどいろんな春の野草が咲く。 |
葭始生 | 葦が芽を吹き始める |
| 霜止出苗 | 霜が終り稲の苗が生長する | ||||
| 牡丹華 | 牡丹が咲く | ||||
| 立 夏 | 5/5 | 45 | 新緑が美しく、吹く風にも夏の気配が感じられる。 この日からは「初夏」という。水田に水がはられ、かえるも鳴きはじめる。 |
蛙始鳴 | 蛙が鳴き始める |
| 蚯蚓出 | ミミズが地上に這出る | ||||
| 竹笋生 | 筍が生えて来る | ||||
| 小 満 | 5/21 | 60 | 万物が長じ、天地が満ち始めるという意味。 晴天なら、麦がよく実るというので「麦生日」ともいわれる。 スイバ、ギシギシ、チガヤ、ノビルなど丈の高い草が生き生き育つ。 |
蚕起食桑 | 蚕が桑を盛んに食べ始める |
| 紅花栄 | 紅花が咲く | ||||
| 麦秋至 | 麦が熟し麦秋となる | ||||
| 芒 種 | 6/5 | 75 | 麦を刈り取り、稲を植える頃、(芒は穀類の殻についている毛のこと) 紫陽花、アヤメ、花しょうぶ、野では夏草が生い茂り始める。 |
螳螂生 | カマキリが生まれる |
| 腐草為蛍 | 腐った草が蒸れ、蛍になる | ||||
| 梅子黄 | 梅の実が黄ばんで熟す | ||||
| 夏 至 | 6/21 | 90 | 太陽が北回帰線(北緯23度27分)の真上を通過する日 北半球では昼間がもっとも長くなる。 生い茂る夏草、柴地には可憐なネジバナも咲く。 |
乃東枯 | ウツボグサが枯れる |
| 菖蒲華 | アヤメが咲く | ||||
| 半夏生 | カラスビシャクがはえる | ||||
| 小 暑 | 7/7 | 105 | この日から「暑気」に入ル。暑中見舞いはこの日から。 曇天の野に青いツユクサがより鮮明に咲く。 |
温風至 | 暖い風が吹いて来る |
| 蓮始開 | ハスが咲きだす | ||||
| 鷹乃学習 | 鷹の幼鳥が飛ぶことを覚える | ||||
| 大 暑 | 7/22 | 120 | 梅雨が明け、暑さが一層増してくる。「土用の丑の日・・・27日」には 暑気を乗り切るという意味でウナギをたべる。 ヤブカンゾウ、ノアザミなど夏らしい花が咲く。 イネ科の野草も勢いを増し小花を咲かせる。 |
桐始結花 | 桐の実が生り始める |
| 土潤溽暑 | 土が湿って蒸暑くなる | ||||
| 大雨時行 | 時として大雨になる | ||||
| 立 秋 | 8/7 | 135 | 夏至と秋分の中間、秋の始まりとされるが実際には1年を通し一番暑い。 この日から、残暑見舞いにかわる。 平地では可憐な野の花はあまりなく、エノコログサが繁り、 ガガイモ、ヤブガラシなどのつる性植物がのびている。 |
涼風至 | 涼しい風が立ち始める |
| 寒蝉鳴 | 蜩が鳴きだす | ||||
| 蒙霧升降 | 深い霧が立つ | ||||
| 処 暑 | 8/23 | 150 | 暑さもようやくおさまる頃。この時期を過ぎ、なお暑くなる事を秋暑という。 キツネノマゴが咲き始め、ニラの白い花も咲く。 |
綿柎開 | 綿のガクがひらく |
| 天地始粛 | 暑さもようやくおさまる | ||||
| 禾乃登 | 稲が実る | ||||
| 白 露 | 9/8 | 165 | 道端の野草に白い露が宿るようになり、燕も南へと去る頃。 野にはイヌタデが咲き、コスモスも風に揺れている。 |
草露白 | 降りた露が白く光る |
| 鶺鴒鳴 | セキレイが鳴きだす | ||||
| 玄鳥去 | ツバメが南へ帰る | ||||
| 秋 分 | 9/27 | 180 | 昼と夜の長さが同じになり、この日を中心に前後3日が秋の彼岸。 それにあわせるかのようにヒガンバナが咲く。 |
雷乃収声 | 雷が鳴り響かなくなる |
| 蟄虫坏戸 | 虫が土中に掘った穴をふさぐ | ||||
| 水始涸 | 田畑の水を干し始める | ||||
| 寒 露 | 10/8 | 195 | 秋の長雨も終わり、草木が露を結ぶ頃。暑さも感じなくなり秋が深まってくる。 土手や空き地にススキが穂を垂れ、あたらしい野草はみかけなくなる。 穀類の収穫のとき。 |
鴻雁来 | 雁が飛来し始める |
| 菊花開 | キクが咲く | ||||
| 蟋蟀在戸 | コオロギが戸のあたりでなく | ||||
| 霜 降 | 10/23 | 210 | 秋が一段と深まり、霜がおりることもある。この頃から吹く風を 木枯らしという。高原にはリンドウ、吾亦紅がある。 |
霜始降 | 霜が降り始める |
| 霎時施 | 小雨がしとしと降る | ||||
| 楓蔦黄 | もみじや蔦が黄葉する | ||||
| 立 冬 | 11/8 | 225 | 冬に入るはじめ。北日本、高地では初氷、初霜など冬の便り、 日の光も弱まり、季節風も吹き始める。 |
山茶始開 | サザンカが咲き始める |
| 地始凍 | 大地が凍り始める | ||||
| 金盞香 | 水仙の花が咲く | ||||
| 小 雪 | 11/23 | 240 | 本格的に冬に入っていく頃だがまだ寒さも厳しくなく雪も積もるほどでもない。 | 虹蔵不見 | 虹を見かけなくなる |
| 朔風払葉 | 北風が木の葉を払い除ける | ||||
| 橘始黄 | 橘の葉が黄葉し始める | ||||
| 大 雪 | 12/7 | 255 | 大陸の高気圧の勢力が増し、寒さが厳しくなる頃。 野はベージュ色になるがよく見ると寒さに耐えて咲いているノボロギクや赤く染まったアメリカフウロの葉を見ることができる。 |
閉塞成冬 | 天地の気が塞がって冬となる |
| 熊蟄穴 | 熊が冬眠のために穴に隠れる | ||||
| 鱖魚群 | 鮭の群れが川をのぼる | ||||
| 冬 至 | 12/22 | 270 | 一年でもっとも昼が短い日。かぼちゃを食べ柚子湯に入ると無病息災といわれる | 乃東生 | ウツボグサが芽を出す |
| 麋角解 | 大鹿が角を落とす | ||||
| 雪下出麦 | 雪の下で麦が芽を出す | ||||