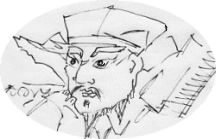”井原線を行く”
6回目 Mar . 27
(早雲の里荏原駅)〜西江原〜野上〜青野〜井原市街(井原駅)
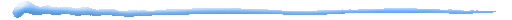
朝から薄曇、夕方から雨の予報だったが比較的暖かいので出かける。
「早雲の里荏原」とは・・・?
北条早雲の生誕地の高越城跡をはじめ史跡が点在しているので
駅名の由来となったとの説明板があった。
前回も通った道を鎌迫池までさかのぼる。緩やかな登りがつづく。
土手の上の木でキジバトくらいの大きさの2羽が騒いでいる。濁った声に最初ゲラかと思ったが
混みあった梢で動き回るので双眼鏡でも全体の姿は確認しにくい。
背は黒く腹のほうは赤茶に見える。ゲラではなさそう。
撮った写真を取り込み拡大すると羽に青い色が見える。
カケスだ!
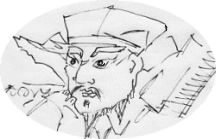
1432年 北条早雲 荏原庄に生まれる
法泉寺
北条早雲の父、高越城主伊勢新左衛門盛定が建てた伊勢氏の菩提寺
門から本堂への階段がなかなかいい。
寺には早雲が寄進した「摺り袈裟の版木」や早雲筆の禁制が残されているそうだ。

 |
|
 |
| 参道の干支の地蔵 |
|
(伝)早雲と父の墓 |
法泉寺を後にし雄神川を上流へと歩く。

川にはキセキレイが多い
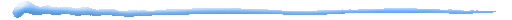
 |
 |
 |
| ナガバタチツボスミレ |
シロバナタンポポ |
ヒメオドリコソウ |
 |
 |
 |
| ヒメウズ |
ヤブツバキ |
ハコベ |
野の花も種類が増えてきた。川沿い、神社などにはヤブツバキが美しい。
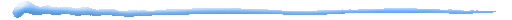

道路沿いにあった諏訪宮
しめ縄が竜というのは珍しい。眼が紅白の豆電球というのも愉快。

1185年 那須与一は屋島の合戦で扇の的を射る。
その戦功により丹波、信濃、武蔵、若狭、備中など五ヶ荘の地頭職を与えられ
没後もここ備中荏原庄には、那須氏により小菅城が築かれ、諏訪神社や袖神稲荷が祀られる。
永祥寺
1387年那須氏により建立された菩提寺

袖神稲荷
与一が扇の的を射る際破り捨てた片袖を奉納したといわれている。
門の右の道を登っていくと左手から水音がする。登りつめ、歩き疲れた頃に明治池に出る。
明治池の前に道祖渓への入り口がある。
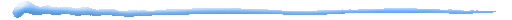
案内板の横から急な階段を下る。
道祖渓
小田川支流の雄神川上流500メートルにわたって出来た渓谷で輝緑石の台地である雄神台と雄宝台の間を
永祥寺の南へと流れ出ている。落差が大きく明治池からの水が多くの滝や淵を形成している。
上部より、竜門の滝、鬼が淵、河鹿の里、竜王の滝、見底の滝、座禅岩など周囲の木々とともに渓谷美をかもしだす。
道祖渓の名の由来は案内板の説明によると
永祥寺開山実峰道師を慕って集った童子のなかに道祖神の化身である稚児がいたという伝説からとか。
 |
|
 |
| 竜門の滝 |
|
竜王の滝 |
滝と渓谷を楽しんで遊歩道を行くと再び永祥寺前へ出る。
ここから坂道を青野町へ
登りきったらブドウ畑が開けた。
青野町は標高200mのブドウの里
ちょうどブドウ棚の準備中だろうか新しいビニールの屋根を張り始めていた。
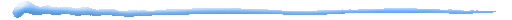
空模様が怪しくなってきた。井原市街へと急ぐ。
市内の興譲館高校の門はめずらしい。
門前の案内板によると
庶民子弟の教育の場として1853年(嘉永6年)一橋家と郡内有志が
儒学者阪谷朗廬を招き開校したとある。
構内には当時に植えられた紅梅の古木が美しい花を咲かせていた。
メモ
(興譲館について)
1697年に藩校となった米沢藩の興譲館をはじめ、小城藩(佐賀)、徳山藩、荻野山中藩(神奈川)はそれぞれ藩校
その他、甲斐の谷村、私学の備中とで幕末には6箇所にあった。そのうち現在も高等学校として残っているのは
米沢と岡山である。ただし広辞苑では興譲館として藩校のみが紹介されている。
井原駅へは小田川をわたる。カワウ、カイツブリが泳ぎ、中州の茂みからカワセミが飛び立つ。
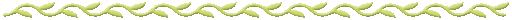
総社〜清音〜川辺宿〜吉備真備〜備中互妹〜三谷〜矢掛〜
小田〜早雲の里荏原〜井原〜いずえ〜子守歌の里高屋〜御領〜湯野〜神辺
![]()
![]()