
”井原線を行く”
8回目 Apr .24
高屋町(子守唄の里高屋駅)〜高屋〜(県境)〜上御領〜西中条〜下御領〜湯野(湯野駅)
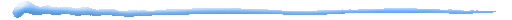
きょうは八丈岩のある御領山の山裾を歩くことにした。
見上げると 緑、みどり、ミドリ
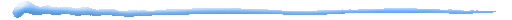
高屋駅から旧山陽道を広島との県境へ向かう。
旧街道沿いは古い家並みが残っている。しばらく歩くと境の石塔がたっている。
 |
|
 |
| 高屋 |
|
岡山、広島の県境 |
街道を右に折れ、清水川沿いを奈良原方面へと登る。道の両側にはウマノアシガタやスミレが美しい。
そろそろノアザミも咲き始めた。

カワトンボ

溜池の近くにあった堺岩
説明によると封建時代は山は領主のものであったが時には村人たちを入山させ山菜とりをさせた。しかし封建制が崩壊すると
村々は自然の恵みを競ってテリトリーを守ろうとそれぞれに境界をもうけこのような岩を置いたとあった。
彫られていた文字が境ではなく「堺」であるのがおもしろいと思った。
山桜はほとんどが散ってしまったがコバノガマズミやサイフリボクといった白い花が美しい。
フジも咲き始めた。
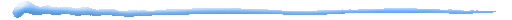
四季の森と名づけられた園地より八丈岩を見上げる。
<八丈岩の鬼伝説>
むかし、御領山山頂には栗が沢山しげっていた。高屋川をはさんで向かいの山、権現山は岩山で
それぞれ鬼が住んでいた。ある時山の高さをきそって喧嘩となり
それぞれ、栗と岩を投げ合い御領山は岩だらけ、権現山は栗山となった。
そしてこの御領山は投げられた岩のぶんだけ高くなった。
ちなみに八丈岩のある御領山は234.2メートル、権現山は231.4メートルだそうな〜〜

四季の森より堂々川に沿って下御領へとくだる。

堂々公園
ここ神辺町には土石流災害を防ぐ砂留めがたくさん残っていて古いものは江戸時代に築造され40基ちかくが
現存するそうで、堂々川流域にも8基ありこの公園下にあるものは最大だそうだ。
旧山陽道ちかくまで下った角に備後国分寺跡がある。

奈良時代全国66箇所に建立された国分寺の一つで説明によると発掘調査により
東西150mの寺域が判明、講堂、金堂、塔跡と南門跡の検出により法起寺式伽藍配置をなすことがわかったとある。
現在の建物は約300年前の再建だそうで古代山陽道に面した南門跡から今の山門にいたる道沿いの
松が美しかった。

いよいよ次回は終着、山陽道の宿場町神辺へ
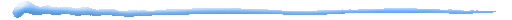
総社〜清音〜川辺宿〜吉備真備〜備中互妹〜三谷〜矢掛〜
小田〜早雲の里荏原〜井原〜いずえ〜子守歌の里高屋〜御領〜湯野〜神辺
![]()
![]()



















