|
シダ植物
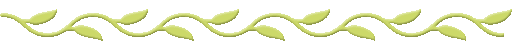
種子を形成しない植物のうちでは最も高等。植物体は完全に根、茎、葉を備えている。維管束(根、茎、葉を貫く管組織で、水分を運ぶ導管のある木部と養分を運ぶ古い管のある師部がある。)がよく発達し、多くは陸上に生える。
胞子による無性世代(胞子体)と、受精による有性世代(配偶体・・・前葉体)が交互に繰り返される。
胞子体が生活史の中心である。
生活環
| 胞子体 |
前葉体 |
| 根、茎、葉を持つ |
一般に0.5~2cmのハート型の
葉状体で、仮根を持つ |
| 無性生殖によって胞子を作る |
(精子と卵細胞を作り)
有性生殖によって受精卵を作る |
| 胞子は発芽して前葉体となる |
受精卵は成長して胞子体となる |
シダの観察には、
・葉の切れ込み方・色合い・根茎の様子(直立、斜上、はう)・ソーラス(胞子曩群)の苞膜の形と位置。
・葉柄や葉軸につく鱗片の形などが必要とされている。
世界に10000種、日本には500種ほどある。と聞いている。
ここでは
野山でみつけたものの名前を知りたくて調べ、載せていますが
素人の趣味のページですので,まちがった情報もあるかもしれません。
まちがいを発見された場合ご一報いただければ幸いです
トクサ科、ヒカゲノカズラ科、イワヒバ科、ハナヤスリ科、ゼンマイ科、カニクサ科、ウラジロ科、コケシノブ科、
ヘゴ科、オシダ科、シシガシラ科、シノブ科、ワラビ科、ウラボシ科、サンショウモ科
参照した本:保育社「しだの図鑑」ほか
|

スギナ◎
★シダ植物・トクサ科
★生育地は草地や土手 分布:北海道~九州
★スギナの茎のたかさは30~40cm、スギナの葉に見えるのは枝で
輪生している。地下茎から胞子をつけるための茎、ツクシを出す。
★ツクシの茎先の穂で胞子ができる。
穂の長さは2~4cm。胞子は発芽して雌雄異株の前葉体となり、
造卵器と造精器ができ、卵細胞と精子を作る。
これが受精して発芽すると新しいスギナになる。
★ツクシの出る時期:3~4月 |

ヒカゲノカズラ◎
★シダ植物・ヒカゲノカズラ科
★生育地:山地林下の地上 分布:北海道~九州
★茎は直径3~4mmの長いひも状。茎には
長さ4~5mm、幅1ミリ弱の葉が密生し、
全体として 6~8mmの太さになる.
★茎先から7~20㎝の柄を出し、2~3に枝分かれして円柱状の
胞子のう穂をつける。
★穂の出る時期:6~7月
☆撮影:6月27日森林公園 |

オオハナワラビ◎
★シダ植物・ハナヤスリ科
★生育地:山地のやや湿った林内
分布:本州~沖縄
★茎は15~50㎝。葉を年1個出し、夏は枯れる。栄養葉は3回羽状に深裂し、やや厚く、草質。縁は鋭鋸歯
葉柄や羽軸に長い毛が散在する。
★胞子葉は長く、上に伸び、丸い玉を多数つける。
胞子は秋に熟する。
☆撮影:10月8日道後山
|


ワラビ◎
★シダ植物・コバノイシカグマ科
★生育地:日当たりのいい原野
分布:日本全土
★根茎は地中を長くはい群落を作る。草丈1~2m
葉は草質。葉身は三角形、2~3回羽状複葉で、最下片が最大になる。
小羽片の先は分裂せず、尾状になるのが特徴。
裂片はわずかに内側に巻く。葉の裏面は多毛
★ソーラスは葉の縁に沿って線状につく。包膜に辺毛がない。
根茎で増え、ソーラスは稀にしかつかない。
☆撮影:5月8日 草間台 |


ゼンマイ◎
★シダ植物・ゼンマイ科
★生育地:平地、山地の林縁
分布:日本全土
★根茎は太く、腐りにくく、オスマンダと呼ばれ、
ラン栽培などの園芸材料として使われる。草丈0.5~1m
葉は2つの形があり、共に春、綿毛につつまれ伸びる。
栄養葉の若葉が山菜となる。厚く、無毛。葉身は2回羽状複葉、三角状披針形 で、最下部の羽片が最大。小羽片は全縁で、基部は切形。
胞子葉は4月に出て、初夏には枯れる。胞子は葉緑体があり緑色
☆撮影:5月8日 草間台 |

シシガシラ◎
★シダ植物・シシガシラ科
★生育地:林下、特に斜面を好む。
分布:日本全土(日本固有種)
★太い根茎があり、放射状に葉を広げるが、斜面に生育していることが多く、斜面方向に葉が垂れ下がる傾向がある。常緑で単葉
冬はロゼット状に地表面にへばりついている。
春になると、新芽は赤く、中心に立ち上がって美しい。
栄養葉と胞子葉を形成する。
胞子葉は長柄があり、高く、幅が狭く、羽片も狭い。
栄養葉は基部と先端が細くなる。羽片の中肋の表面が溝になり、
裏面に隆起がある。ながさは40センチ前後
☆撮影:5月13日 神石高原
放射状に出た葉の中心あたり、先端がまだ丸く葉を巻いていて
柄が伸びているのが胞子葉であろうと思う。
|

クラマゴケ◎
★シダ植物・クラマゴケ科
★生育地:山地の林下
分布:本州、四国、九州
★地をはう常緑性のシダ。
主軸は細く、長く匍匐し、担根体があり、葉はまばらにく。側枝は短く、
幅が広い。葉は緑色~黄緑色縁で、縁に微細な鋸歯がある。
栄養葉は2形が、4列につく。
腹葉は卵形、横に開出して2列に並び、
背葉は小形で、前向きに2列に並ぶ。
胞子嚢穂は長さ0.5~1.5cm、側枝の先につき、細い四角柱状。
同形の葉が4列にならぶ。
|

ヒメクラマゴケ◎
★シダ植物・クラマゴケ科
★生育地:やや日の当たる低山斜面、岩上
分布:近畿以西~九州
★地をはう常緑性のシダ。茎は秋から春の匍匐茎と夏から秋に胞子嚢穂をつける直立茎とに分かれる。
匍匐茎の腹葉は卵形の鋭頭~鈍頭(おにぎり状三角形)、細鋸歯縁でやや密につく。背葉は狭卵形の鋭尖頭、細鋸歯縁で先端は長く伸びて反りかえり、交互にまばらにつく。匍匐茎は晩秋に紅葉する
直立茎の主軸は太く、まばらに側枝をだして葉をつける。胞子葉は、腹側のものは小さく先端が細長く伸び、背側のものは大きく鋭尖頭となる2形で、先端に胞子嚢穂を頂生し、他の部分と区別できる。
|

ウラジロ◎
★シダ植物・ウラジロ科
★生育地:林縁 山地斜面 陽地をこのむ。
分布:本州[福島、新潟県以南)四国、九州 沖縄
★草丈は50~200㎝で常緑性のシダ、葉裏は粉白色
毎年、1対の羽片をつけ、2~3段と丈も高くなり、大きいものは2mに達する。
根茎は匍匐し、太くて長い。
葉柄は長さ30~100cm、緑色、平滑。
一枚の葉は1~数対の羽片からなる。葉は越年して伸びる。
小羽片は深裂し、裂片は線形。
ソーラスは縁と中肋の中間につく。ソーラスに包膜は無い。
☆和名の由来は葉の裏が白いことから |

コシダ◎
★シダ植物・ウラジロ科
★生育地:山地、山麓の日当たりのいいところ
分布:本州[福島以南)四国、九州
★草丈は50~200㎝で常緑性のシダ
ウラジロより小さいのでコシダと呼ばれているが、2分岐を繰り返し、
何段にもなって高さ2mを超えることもある。
根茎は長く、匍匐する。
葉は硬く、黄緑色、葉の裏面は粉白色。
鱗片、毛はない。光沢がある。
裂片の先は凹になることが多い(マウス)
ソーラスは辺縁と中助の中間につく。
|

ヤブソテツ◎
★シダ植物・オシダ科
★生育地: 山地、
分布:北海道南部以南
★草丈は50~00㎝で常緑性のシダ
★根茎は直立し、塊状で、葉は叢生する。
葉は葉質がややうすめの厚紙質で光沢は一般に少なく緑から灰緑
葉は単羽状葉で長さ20~40㎝。頂羽片には鋸歯があり、
縁が不規則に波打つ。側羽片は15~25対、卵状長楕円形。
中部の羽片は大きくとも長さ8㎝、幅2㎝程
羽片基部の耳垂はほとんどない。
裏につく包膜は灰白色で丸い。
仲間に、オニヤブソテツ、ヒロハヤブソテツ、などがある。
|

ノキシノブ◎
★シダ植物・ウラボシ科
★生育地:民家の樹幹、石垣など
分布:北海道南部、本州、四国、九州
★草丈は12~30で常緑性のシダ
根茎から密生し葉柄は濁った褐色で短い。(1~3㎝)
葉は単葉、革質、長さ10~20㎝、幅0.5~1㎝程。中肋は裏面に少し隆起する。
ソーラスは2㎜前後の円形で葉身の先1/2の部分に、葉の半分の幅に
並んで付く。
ウラボシ科は世界に1,000種あるといわれている。
似たものにミヤマノキシノブ、ヒメノキシノブ、ツクシノキシノブなどがある。
|


クモノスシダ◎
★シダ植物・チャセンシダ科
★生育地:林下の崖、石垣、石灰岩地
分布:北海道、本州、四国、九州
★石灰岩質を好み、岩の隙間にはえる。
茎はごく短く、長さが20cmまでくらいの単葉をロゼット状につける。葉は狭披針形から狭三角形で、短い葉柄がある。縁に鋸歯はないが、波打つようになることもある。葉の先端は細くなって伸び、ツル状になってその先端が基盤上につくと、そこから芽を出す。胞子のう群は細長くて長さ5mmまで、不規則に2列。葉裏の主軸から斜めに外側に伸び、薄い包膜がある。
|

ハカタシダ〇
群生はしていたが出始めの幼いものだと思われる。
★シダ植物・オシダ科
★生育地:山地の林下
分布:本州(茨城県~新潟県以西)、四国、九州
★根茎は短く匍匐する。葉柄は長さ20~65㎝。葉身は濃緑色で、光沢があり、硬い紙質、長さ20~60㎝、幅15~40㎝、2回羽状複葉、葉の先は、頂羽片が明瞭。羽片は間隔が広く、3~5対(3対が多い)。羽片の幅は狭く、最下羽片の下向き第1小羽片が長い。小羽片は先が尖った鋸歯があり、脈がはっきり見える。ソーラスは裂片の縁と中肋の中間につく。包膜は褐色~暗褐色、円腎形、全縁。
葉に斑入りが多い。
|

イノモトソウ◎
★シダ植物・イノモトソウ科
★生育地:山地、人里
分布:本州(福島~能登以南)、四国、九州
★根茎は短く、横向きか斜上。草丈は20~60センチ
葉は2形あり、淡緑色で草質。上部中軸に沿って翼があるのが特徴。
胞子葉は葉柄が長く立ち上がり、ソーラスは全縁の葉の縁に出来る。
栄養葉の羽片や裂片の幅は約5mm。
|

オオバノイノモトソウ◎
(小さい個体)
★シダ植物・イノモトソウ科
★生育地:山麓、林下
分布:本州(福島以西)、四国、九州
★根茎は 根茎は匍匐し短い。横向きか斜上。草丈は20~60センチ。常緑。
葉柄はわら色~褐色で基部鱗片は褐色。
葉は1回羽状複葉で頂羽片がある。羽片の辺縁は鋸歯状で基部が中軸に流れて翼とならない。葉は2形で、胞子葉は栄養葉より葉柄が長く、葉幅が細い。ソーラスは羽片の辺縁に沿って長くつく。
|

イワガネソウ〇
★シダ植物・ホウライシダ科 (常緑)
★生育地:山麓、林下の湿った場所、川沿い
分布:本州、四国、九州
★根茎は匍匐する。葉柄は長さ30~50㎝。80cm前後の葉をつける。葉身は1~2回羽状で脈は網目を作る。羽片の先は次第に細くなり,全縁又は細鋸歯。ソーラスは脈に沿って網状につく。
|


リョウメンシダ◎
★シダ植物・オシダ科
★生育地:山地の谷間、林内
分布:全国
★草丈は60~150センチ
根茎は短く、這う。葉は黄緑色から明るい緑色で、3回羽状複葉。葉質は紙質、羽片にしわがあり全体に縮みしわがあるように感じる。葉柄下部の鱗片は淡褐色で密生する。ソーラスは葉の下部中央から外に向かって順番に中肋寄りにつく。
葉の両面が同じ色をしているところからリョウメンシダという。
|

ミツデウラボシ◎
★シダ植物・ウラボシ科
★生育地:岩の上や路傍の崖
分布:北海道南西部以南の暖地
★側脈がぼやけた黒線状。葉縁に細い黒色部。葉の形はさまざまに変化し、単葉もあリ、下部が広がっている。大きな葉では基部が鉾型あるいは紅葉型。
乾燥に強い。ソーラスは丸い。
|
|













































